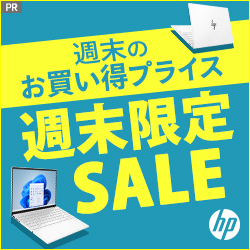日本の薄型テレビ市場における2024年1~9月のシェア調査(日経新聞・BCN)によると、中国大手ハイセンス(海信)が40.4%で首位、TCLが9.5%で3位に入り、合計49.9%と約半数を占めた。これは2019年の12.1%、2023年の21.4%から倍増し続ける急成長だ。一方、ソニーは9.7%で2位、パナソニックは9.0%で4位にとどまり、中国勢が日本勢を大きく引き離している。
中国メーカーがシェア倍増:最新データで見る市場動向
BCN調査:中国メーカーが日本テレビ市場を席巻
日経新聞と家電量販店の販売データを集計・分析するBCN株式会社が発表した最新の市場調査によると、2024年1月から9月における日本の薄型テレビ市場で、中国メーカーの存在感が際立つ結果となりました。具体的な市場シェアの内訳は以下の通りです:
- ハイセンス(海信):40.4%(1位)
- ソニー:9.7%(2位)
- TCL:9.5%(3位)
- パナソニック:9.0%(4位)
特筆すべきは、中国の2大メーカーであるハイセンスとTCLの合計シェアが49.9%に達し、日本の薄型テレビ市場のほぼ半分を占めるまでになっていることです。
BCNのデータ分析によれば、この中国メーカーのシェア拡大のスピードは驚異的です。調査によれば、中国メーカーの日本市場におけるシェアは2019年にはわずか12.1%、2023年には21.4%でしたが、わずか1年で倍増して50%近くまで上昇しました。この急速な成長は、日本の家電市場における構造的な変化を示唆しています。
明らかになった販売チャネル別の動向
BCNの詳細な調査データによると、中国メーカーの躍進は販売チャネル別にも顕著な違いがあります。特にEコマース(オンライン販売)では、中国メーカーの合計シェアが60%を超える結果となっており、オンラインショッピングを好む若年層を中心に支持を広げています。
一方、家電量販店での販売シェアも急速に伸びており、2023年末には約30%だったものが、2024年9月には45%近くまで上昇しています。BCNのアナリストによれば、この背景には家電量販店側の品揃え戦略の変化があり、中国メーカー製品の店頭展示スペースが拡大していることが指摘されています。
また、BCNが実施した消費者意識調査では、テレビ購入時の決め手として「価格」を挙げる回答が前年比10ポイント増の68%となり、「ブランド」(前年比5ポイント減の42%)を大きく上回る結果となりました。この消費者意識の変化が、コストパフォーマンスに優れた中国メーカーの躍進を後押ししていると分析されています。
製品価格帯別シェアの変化
BCNの価格帯別販売動向調査によると、特に顕著な変化が見られたのは5万円未満の中低価格帯です。この価格帯では、中国メーカーの合計シェアが70%を超えており、日本メーカーは苦戦を強いられています。
具体的には、32インチから43インチの中型テレビ市場では、ハイセンスのシェアが50%を超え、TCLと合わせると80%近くを占めるという圧倒的な状況となっています。一方、10万円以上の高価格帯では依然として日本メーカー、特にソニーが優位を保っていますが、この価格帯自体の市場規模が縮小傾向にあるため、全体シェアへの影響は限定的です。
BCNのアナリストは「中国メーカーは単に価格が安いだけでなく、画質や機能面でも日本メーカーと遜色ない製品を提供できるようになっている」と分析しており、この「コストパフォーマンスの高さ」が消費者の支持を集めていると指摘しています。
地域別・年齢別の購買傾向
BCNの調査では、地域別・年齢別の購買傾向も明らかになっています。都市部、特に首都圏と関西圏では中国メーカーのシェアが高く、東京都内の一部エリアではハイセンスとTCLの合計シェアが60%を超えるエリアも存在します。
年齢別では、20代から30代の若年層における中国メーカー選好が顕著であり、この年齢層では「ブランドよりもスペックと価格」を重視する傾向が強く見られます。一方、60代以上の高齢層では依然として日本メーカーへの信頼度が高いものの、この層でも徐々に中国メーカー製品の購入率が上昇しているとBCNは報告しています。
ハイセンスの勝因:レグザ買収とブランド二本立て戦略


- レグザ買収効果:ハイセンスは東芝映像ソリューションの「レグザ」ブランドを取得し、資材調達と事業部再編でコスト削減と品質向上を同時に実現した。
- デュアルブランド戦略:高付加価値の「レグザ」と低価格帯の「ハイセンス」ブランドを使い分け、幅広い顧客層を獲得している。
TCLの浸透力:量販店からECまで幅広く

TCLも9.5%のシェアを獲得。AmazonなどECサイトだけでなく、家電量販店やディスカウントストアにも積極展開し、「手頃な価格で妥協しない画質」を訴求して支持を拡大した。
最新週間ランキングが示す中国ブランドの勢い
BCN+Rの薄型テレビ週間売れ筋ランキングを見ると、2025年4月第4週時点でハイセンスが常にトップ3に入り、TCLやシャオミも上位に顔を見せている。たとえば4月21~27日のランキングでは、32型以下の部門でハイセンスが2位、シャオミが5位にランクインした(BCN+R)。
メーカー別週間シェア推移
- ハイセンス:2025年4月には週次販売台数の約15~20%を占める。
- TCL:同期間で約7~10%を安定して確保。
- シャオミ:参入直後ながら5%前後で推移し、今後の伸長が期待される。
これらの数字は年間集計の49.9%と整合し、中国メーカーの地盤が週次ベースでも確立されていることを裏付ける。
薄型テレビ 週間売れ筋ランキング(BCN+R)
https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type%3D100 BCN+R
歴史的背景――中国テレビ産業と日本技術の深い関係
中国メーカーが日本で支持を得る背景には、かつての技術導入の経緯がある。2000年代前半、中国国営企業は東芝・日立・三洋・パナソニックから製造ラインや部品を輸入し、技術を吸収してきた。農村向け補助金政策「家電下郷」、都市向け「以旧換新」により薄型化が急進展し、品質も向上した。とはいえ「日韓ブランド志向」は根強く、日本市場でのシェア奪取は極めて異例の出来事といえる。
中国国内市場の飽和と海外シフト
国内販売台数は2020年以降減少基調で、2024年は約3,085万台にとどまる(AVC調べ)。補助金なしではマイナス成長が続き、国内に明るい材料が少ないため、中国メーカーは海外展開を強化。日本は高品質志向市場として格好のターゲットとなった。
新たな挑戦者――シャオミの日本参入
日本市場に本格参入したシャオミは32インチスマートテレビを約2万円強、100インチの超大型スマートテレビを20万円弱で投入。圧倒的なコスパで話題を呼び、今後口コミでさらにシェアを拡大する可能性が高い。
今後の展望と日本メーカーへの示唆
- ハイエンド戦略の可能性
シャオミがそうであったように、中国勢は低価格からスタートし技術力を蓄積後、ハイエンド製品で再参入するパターンをたどる可能性がある。 - 日本勢の対応策
— 差別化強化:独自の映像技術やサービスとのセット販売
— コスト見直し:サプライチェーン再編による価格競争力向上
— ブランド価値訴求:日本品質を再定義し、プレミアム市場での優位性を確保
まとめ
日本の薄型テレビ市場で中国メーカーが合計49.9%のシェアを獲得し、“家電は日本製”の常識が揺らいでいます。ハイセンスのレグザ買収によるブランド強化、TCLやシャオミの低価格攻勢が功を奏し、日本勢は価格競争と差別化の両面で新たな戦略を迫られています。今後、中国メーカーが技術力を前面に出したハイエンド機を投入すれば、さらなる市場変動が予想され、日本メーカーはイノベーションとコスト競争力の両立が急務となるでしょう。